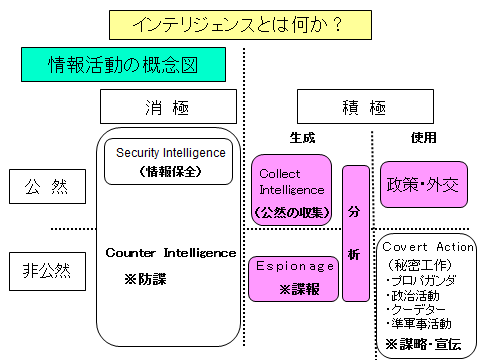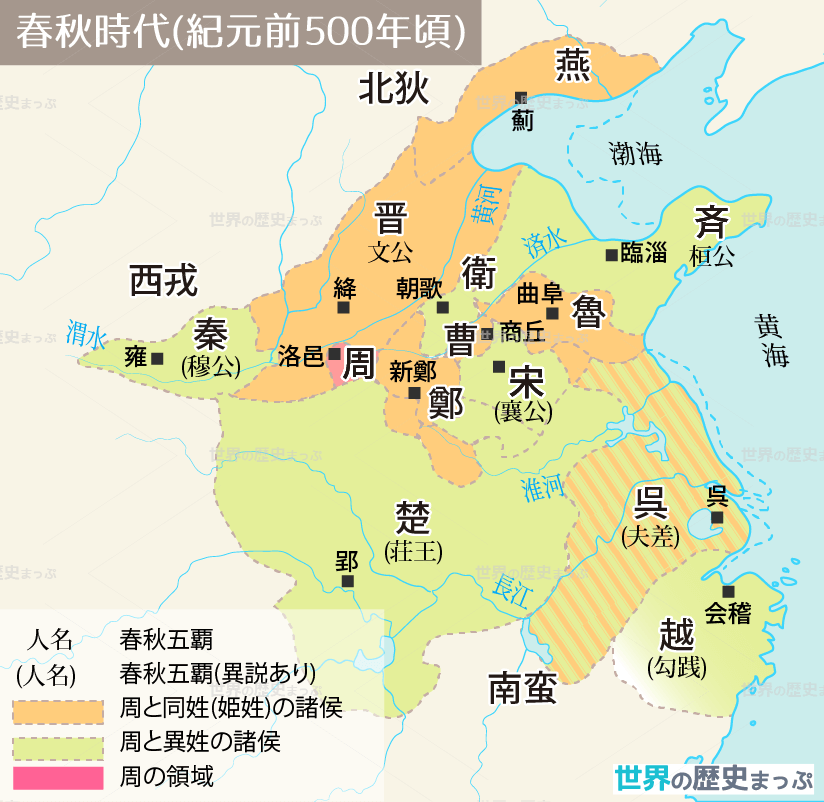情報組織を運用するには経費を惜しむな
『孫子』は戦いには金を惜しんではならないと次のように説いている。
「およそ師を興すこと十万、師を出すこと千里なれば、百姓の費、公家の奉、日に千金を費やし、内外騒動して事を操(と)るを得ざる者、七十万家。相い守ること数年にして、以て一日の勝を争う。而るに爵禄百金を愛(おし)んで敵の情を知らざる者は不人 の至りなり。……故に明主・賢将の動きにて人に勝ち、成功の衆に出づる所以の者は先知 なり。先知は鬼神に取るべからず。事にかたどるべからず。度に験(もと)むべからず。必ず人に取りて、敵の情を知る者なり。
これを訳すると以下のとおりとなる。
戦争には莫大な国家予算がかかり、国民に犠牲を強いる非常事態を数年間も続けることになるが、勝敗は一日の決戦で決まる。こうした費用を出し惜しみせずして、初めて七十万の軍隊を動かすことができる。
情報を取るためのスパイの活用にお金を惜しむことは、戦いに負けて結果的に民衆を苦しめることなる。 それなのに金を使うのを惜しんで、敵に関するインテリジェンスを得ようとしないのは、まったく愚かなる行為である。
ゆえに、聡明な君主や賢い将軍が兵を動かせば、敵に勝ち、成功を得ることで衆人よりも優れているのは、間者を利用して先に知るからである。先知は、祈祷や占などではなく、かならず人によってこそ、敵情を知ることができる。
諜報員をもっとも優遇せよ
また、『孫子』は「故に三軍の事、間より親しきは莫(な)し賞は間より厚きは莫(な)し、事は間より密なるはなし」(用間編)と述べている。
これは、だから、君主や将軍は、全軍の中でも間者(スパイ)を最も親愛し、恩賞は間者に最も厚くし、仕事上の秘密は間者にもっとも厳しく守らせる、という意味である。
戦国武将の織田信長は諜報・謀略を重視した。彼の名を世に知らしめたのは、なんといっても今川義元との桶狭間の戦いにおける大勝利である。
この戦いでは、信長は、なかなか義元の現在地が掴めなかった。そこに、梁田政綱(やなだまさつな)から「義元、ただいま、田楽狭間に輿(こし)をとどめ、昼食中」との情報を越した。これにより、信長は義元を奇襲により討つことに成功した。
信長は、功名第一は梁田、第二は義元に一番槍をつけた服部小平太、第三は義元の首をとった毛利新助(義勝)とした。奇襲のお膳立てをした梁田の諜報・謀略を最も重視したのである。まさに信長は『孫子』を実践したのである。
インテリジェンスは金がかかる
諸外国は情報機関の運用に膨大な費用を掛けている。米国の国家情報機関の予算は500億ドル以上(5兆円以上)。現在のわが国の国家情報機関の費用に関する具体的な情報は不明であるが、おそらく米国とは比べようもない。
情報機関の運用には不透明性がつき物であり、使途不明金もある。エージェントの運用資金などの詳細を明らかにすることはできない。使途不明金は許されないからとして、インテリジェンスにかかる経費が切り詰められれば、「爵禄百金を愛(ほし)んで、敵の情を知らざる者は不人の至りなり」ということになりかねない。まずは国家指導者には「インテリジェンスには金がかかる」ことを認識していただきたい。
旧軍においては明石元二郎大佐の工作活動に百万円の国家予算を充当して、自由に使わせた。明石大佐は地下組織のボスであるコンヤ・シリヤクスなどと連携し、豊富な資金を反ロシア勢力にばら撒き、反帝勢力を扇動し、日露戦争の勝利に貢献しようとした。
当時の国家予算が2億5000万であったことから、渡された工作資金は単純計算では現在の2000億円を越える額であった。明石の活動に国家的支持が与えられていたことがうかがえる。
翻って、今日はわが国はどうだろうか? 十分に情報活動に経費を配当しているだろうか?情報活動に経費を配当し、情報要員を重視しているだろうか?
昭和期の日本軍において作戦重視、情報軽視の風潮が蔓延していたという。現在の自衛隊においてもしかりである。このことを深く認識しているようには思われない。
さいごに
『孫子』が最も強調する点は「勝算もないのに戦うな」ということ、すなわち「戦わずして勝つ」ことである。このための不可欠な要素がインテリジェンスである。
インテリジェンスの役割は無用な争い回避する、あるいは「戦わずして勝つ」ことに寄与すること。つまり、相手国の意図、彼我の能力、環境条件などを把握し、外交によって相手国の譲歩を引き出すための条件を作為することである。
歴史に「仮に」ということはタブーであるが、先の大戦では旧軍が『孫子』を忠実に守り、インテリジェンスを軽視しなければ、敗戦を回避できたかもしれない。すなわち「五事七計」に基づいて、彼我の戦力分析を行えば、無用な戦争はしなかったかもしれない。
日清・日露戦争における勝利以後、わが国では攻勢・攻撃精神が強調され、インテリジェンス軽視という風潮が生起した。日清・日露戦争後の1907年の『国防方針』『用兵綱領』では「攻勢を本領」と確定し、かつ、1909年の『歩兵操典』においても攻撃精神が強調された。
こうした風潮のなかで『孫子』の解釈にも変化が生じたとして、大阪大学・大学院教授・湯浅邦弘氏は以下のように述べる。
「昭和初期から『孫子』を超えた『孫子』解釈が進められ、軍国日本が『孫子』に決別を告げた。……徹底した合理主義に貫かれた『孫子』を曲解し、誤読し、また無視しつつ、精神主義偏重の気風の中で『孫子』の名だけが担がれた。……『孫子』の「君命も受けざるところあり」(九変)が綱領や操典が記す独断専行の肯定に使われ、現実の旧軍の行動に則さない『孫子』の条文は部分否定された」と(湯浅『軍国日本と「孫子」』)。
さらに湯浅氏は、『昭和天皇独自録』から、昭和天皇の戦争分析、「大東亜戦争の遠因」の第一に「兵法の研究が不十分であった事、即(すなわち)、孫子の敵を知り、己を知らねば、百戦危(あや)うからずという根本原理を体得していなかったこと」をあげている。
兵法はその時代、時代に応じた解釈があってしかりであり、また実情に則して応用する必要がある。兵法をビジネスの世界に生かすことも大いに結構であろう。
しかし、必要なことは『孫子』の最大の本質は何かということである。すなわち、本質は「戦わずして勝つ」、次いで「勝ち易きに勝つ」ということであり、そのためにインテリジェンスを重視せよ、インテリジェンスにかかる経費を惜しむなということなのである。インテリジェンスを志す有為な諸氏には、是非このことを肝に銘じてほしい。
以上、『孫子』から、インテリジェンス関連の記述を抜粋しつつ、若干の解説を加えておいた。皆様におかれては、これ以外にも『孫子』からインテリジェンスに関する多くの知見を得ることができると思う。(了)