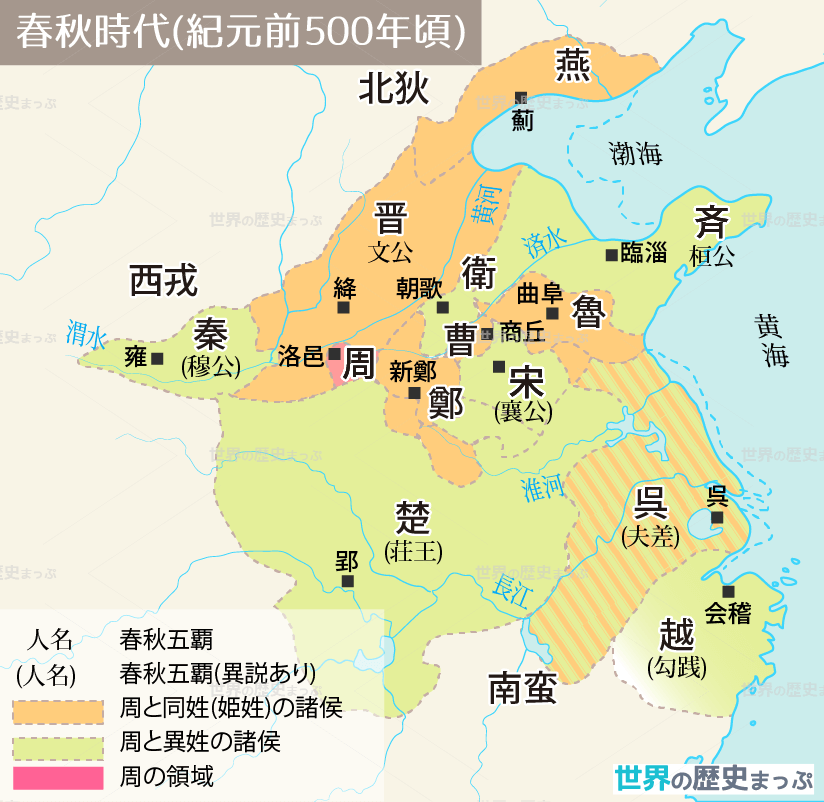インテリジェンスの視点から考察する
平成の大横綱、貴乃花引退
最近のビッグニュースの一つが貴乃花親方の引退騒ぎです。貴乃花は平成の大横綱であり、相撲界の大変な功労者です。世間には衝撃と無念さが走っています。
そもそも、今回の争議の発端は昨年10月の日馬富士暴行事件にさかのぼります。貴乃花部屋の力士である貴ノ岩が、横綱の日馬富士から暴行を受けました。この事件に対し、貴乃花親方は相撲協会ではなく、警察に届け出ました。 貴乃花としては、警察にゆだねなければ、事件がうやむやにされると判断したのでしょう。
他方、相撲協会側としては、事件を調査して公表する立場にありました。しかし、貴乃花親方が相撲協会と貴ノ岩の面会を認めないなど、調査には断固として応じませんでした。
相撲協会側は、「巡業中の事件である。相撲協会の一員であり、しかも巡業部長であった貴乃花が相撲協会に事件を報告するのは当たり前だ」などと論じました。
両者の対立が深まり、相撲協会は貴乃花親方を処分し、日馬富士は引退に追い込まれました。
理事長選挙で敗北
こうした対立が続くなか、本年2月、今後の角界を大きく左右する相撲協会の理事選の選挙が行われました。貴乃花一門は、貴乃花親方が再出馬することに反対して、阿武松(おうのまつ)親方を立てました。
しかし、貴乃花は個人で理事選に出馬します。結局、獲得票はわずか2票で落選します。
その結果、貴乃花親方は本年6月に一門を返上し、無所属になりました。一方、理事に当選した 阿武松親方は8人のグループ (阿武松グループ) を形成しました。
これで、5つの一門と、一つのグループ、そして無所属が貴乃花親方含む4人となったのです。
貴乃花親方、一兵卒からやり直す
貴乃花親方は本年3月に内閣府へ「日馬富士の事件で相撲協会が適切な調査を行わなかった」旨の告発状を提出しました。ここに、いったんは両者の政治闘争の幕が切って落とされたのです。
しかし、ここで想定外のことが起きました。貴乃花部屋の力士である貴公俊(たかよしとし)が付き人に暴力を加えたのです。
この時、すでに日馬富士は暴力事件の責任を取る形で引退しています。だから暴力を振った貴公俊も退職するのが筋ということになります。
貴乃花親方は 貴公俊に相撲を取らせていた一心で 告発状を取り下げました。つまり、貴乃花親方は相撲協会に許しを乞うたわけです。
貴乃花は理事から5階級下の年寄に降格し(理事、副理事、役員待遇、委員、主任、年寄)、「一兵卒からやり直す」と称して、相撲協会の審判部に所属してその職務に精励していました。
貴乃花、引退届を提出
しかしながら、相撲協会と貴乃花親方の対立は完全解決には至らず、水面下でくすぶっていました。
9月25日、貴乃花親方は相撲協会に引退届を提出し、都内で記者会見をしました。年寄を引退し、所属力士は千賀ノ浦部屋に所属先を変更するというものです。
これは突然の事態というわけではありません。といういのは、マスコミが「相撲協会が親方はすべていずれかの一門に入らなければならないこと決定した。その期限が9月27日になっている」などと報道していました。また、すでに 阿武松グループの8人と無所属の3人は二所ノ関一門などに所属していました。
そして、唯一所属先が未定となった貴乃花親方は9月22日、「所属先はどうするのか」という報道陣の質問に対し「それは答えられないです」と発言していました。さらにマスコミは、貴乃花親方の所属先が決まらなければ、厳罰や部屋の取り潰しなどの可能性を示唆していました。
つまり、マスコミやわれわれも貴乃花親方の去就に注目していましたし、貴乃花親方がこの理事会の決定に従わなければ厳罰がある可能性を認識していたのです。
相撲協会もこうした動向はすべて承知しつつ、貴乃花親方の次なる行動を注視していたわけです。
圧力があったと旨を主張する貴乃花
貴乃花親方の引退の理由は、相撲協会から「告発状は事実無根な理由に基づいてなされたもの」と結論付けられた揚げ句、これを認めないと親方を廃業せざるを得ないなど有形・無形の要請(圧力)を受けたというものです。
貴乃花親方によれば8月7日、相撲協会から依頼された外部の弁護士の見解を踏まえたという、 「告発状は事実無根な理由に基づいてなされたもの」との文書での書面が届けられたようです。
これに対し、貴乃花は告発状の内容は事実無根でないことを説明したが、上述のような有形・無形の要請があったということのようです。
貴乃花親方の主張の要点は次のとおりです。
相撲協会はすべての親方は一門のいずれかに所属しなければならず、一門に所属しない親方は部屋を持つことができない旨の決定がなされたようだ。
自分は一門に所属していないので、このままだと廃業になる。
一門に入るよう説得は受けたが、同時にいずれかの一門に入る条件として、告発状の内容は事実無根な理由に基づいてなされたものであると認めるよう要請(圧力)を受けた。
しかし、自分は真実を曲げて、告発は事実無根だと認めることはできない。だから引退届を提出した。
相撲協会側は圧力を否定
これに対して相撲協会側が圧力の介在をまっこうから否定しました。これも周囲の予想通りの対応です。
ここで芝田山(元横綱・大乃国)広報部長が窓口に立ちます。
芝田山親方の言い分は次のとおりです。
7月末の理事会で全親方が5つある一門に所属するという決議をした。これは、予算使用の透明性など、相撲協会のガバナンスの強化が目的である。
告発状が事実無根であることを認めないと一門にいれないということわけではない。そういったことを言って貴乃花親方に圧力かけた事実はない。
一門に所属しない親方がやめなければならないという事実はない。
5月に貴乃花から3月の告発状のコピーの提出を受け、「間違っている点があれば指摘ほしい」との貴乃花親方の発言に応じて、相撲協会が顧問契約のない法律事務所に検証作業を依頼した。
(なお、貴乃花親方から同コピーを提出したのか、相撲協会から提出を要請されたのかかは明らかにされていませんが、相撲協会は全親方に貴乃花親方の告発状を全員に配布したとの報道が以前にありましたので、相撲協会側が提出を求めたものとみられます)
その検証を踏まえ、告発状の主張は「事実無根の理由に基づいてなされた」と貴乃花親方に書面で伝達した。なお、同書面には事実無根と認めるよう貴乃花親方に要請する表現は一切ない、
さらに、報道によれば、相撲協会の意向は 、9月27日に開かれる理事会の時点で、所属一門が未定の親方がいた場合は、その日の理事会で協議する。期間をとって一門への招請を調整するというものだったようです。
本当なのかどうかはわかりませんが、いささか後付けの印象を受けます。
世間には貴乃花親方の早合点を指摘する声があるが
一部には、貴乃花親方は思い込みが強いので相撲協会の対応を勝手に圧力だと誤解した」などの意見が出ています。
これには、貴乃花親方にまだ相撲協会に残ってほしいとの、幾分かの期待値がふくまれているのでしょうが、少なくとも貴乃花親方がありもしない圧力を圧力だと誤解した、早合点したなどは、ありえないことだと考えます。
相撲協会が、貴乃花親方を相撲協会から排除しようとまでは考えていたかどうかはわかりません。しかし、相撲協会の内部において、「反協会派である貴乃花親方の行動を統制・牽制する必要がある。二度と勝手な行動はさせない」との意図があったと考えるのは極めて自然です。
「親方全員の一門所属制度」もガバナンスの強化というよりも、貴乃花親方の反協会的な行動をとらせないための措置であったと考えるほうがしっくりときます。
つまり、 8月に貴乃花親方に提出された「告発状は事実無根だった」との通知は、9月27日までに一門に所属しなければならないとの決定事項とセットであり、いわば「告発状は事実無根だ」と認めることが一門に所属するための“免罪符”であったとみられます。
すなわち、圧力は存在したと考えます。
誰が圧力を掛けたのか
親方全員が一門に入らなければならないということも、文書で通知されたわけでくなく、理事を通じての口頭伝達で行われたようです。相撲協会の言い分では、こうした決定事項は文書で行わないのが慣例なのだそうです。
おそらく貴乃花親方に対しての伝達は、以前に貴乃花一門であった阿武松理事を通じておこなわれたのでしょう。その際、 阿武松親方は貴乃花親方に一門に入るよう真摯に説得を試みたのでしょう。
この際、 阿武松親方 は圧力を掛ける気持ちはなかったと考えます。
ただし、他の理事が間接的に阿武松親方 に対し、貴乃花親方が一門に入るための条件として、「告発状は事実無根であった」ことを認めさせるよう要請した可能性は否定できません。
阿武松親方自信も親方業を続ける、さらに理事として残るために二所ノ関一門に所属しました。そのような立場にあった 阿武松親方が、「貴乃花さん、あなたも一門に入って一緒にやっていこうよう。ただし、一門に入るためには、告発状は事実無根だったと認めないと、一門の他の親方衆はなかなか受け入れてくれるないよ」くらいのことは言った可能性はあると判断します。
無論、芝田山親方が言うように相撲協会が表面的に圧力を掛けた形跡はありません。しかし、これは貴乃花親方に不満を持つ理事や親方衆が生み出した組織全体の暗黙の圧力だといえます。そもそも圧力というものは、無言の圧力がもっとも多いのであり、もっとも効果があるのです。
貴乃花親方がこうした周囲の環境を有形・無形の圧力と認識し、それをもはや回避できない脅威であると感知して、「窮鼠猫をかむ」の言葉どおりの行動に出たのでしょう。
逃げ道が閉ざされた時に、圧力を掛けられた側は乾坤一擲に反撃にでます。それが、今回の相撲協会側と貴乃花親方の対立の縮図であると考えます。
暗黙知の世界で生きた貴乃花
暗黙知とは主観的で言語化することができない知識のことをいいます。言語化して説明可能な知識(形式知)に対する対比語です。
たとえば、歩行や自転車の乗り方は言葉では容易に説明できませんが、脳がその行動を知識として記憶しています。
最近では、暗黙知はビジネスの世界でよく使われる言葉です。徒弟制度のように体で技術を覚えるのではなく、マニュアル化できるものはマニュアル化する、すなわち形式知にすることが重要であるという文脈として使われることが多いようです。
相撲界の四股はまさに暗黙知であると思います。そして相撲界は全体は、明確な規則による定めや、理論的な解釈よりも、過去の伝統や経験に基づく暗黙知が組織全体を支配してきたと考えます。
貴乃花親方は15歳の頃から相撲界に入り、四股を中心に想像を絶する稽古を重ねて横綱になりました。 つまり、貴乃花親方自身も、暗黙知が支配する世界のなかで、経験や勘に基づく生き方や判断力を蓄えてきたのです。
情報分析の世界にもある暗黙知
情報分析の世界ではアルゴリズムとヒューリスティックという言葉が存在します。前者は、
「人間やコンピューターに仕事をさせる時の手順」の意味であり、一歩ずつ手順を経て解答を導き出す思考法です。論理的思考に該当します。
他方、ヒューリスティックは「自己の直感や洞察に基づき、複雑な問題に対する、完璧ではないがそれに近い回答をえる思考法」という意味で用いられています。これは、必ず正しい答えが導きだせるわけではありませんが、ある程度に近い答えを出せる方法です。思考法としては創造的あるいは直感的思考法に該当します。
ヒューリスティクは迅速に答えを導きだすことができますが、思い込みや心理的なバイアスが介在して誤判断することがあります。だから、ヒューリスティクはバイアスの排除に努力しなければなりません。
実は、このヒューリステイクは暗黙知と非常に類似しています。つまり、経験や勘を蓄えて身に着ける思考法です。
情報分析においてはアルゴリズムとヒューリスティクの併用が重要だといわれます。つまりアルゴリズムだけで、迅速に正しい判断ができません。さらに驚くべきは、実は、専門家や経験者によるヒューリステイクの方がアルゴリズムよりも正解率が高いといわれるのです。
貴乃花親方は誤判断だったのか
今回の貴乃花親方の決断は、9月場所終了後の短期間で行われたことから、ヒューリスティクの判断だったとみられます。
上述のように、その判断は誤解である場合もありますが、多くの場合は正しい場合が多いのです。貴乃花親方が、他の事項についてヒュリスティックによる直観的な判断をしたならば、それは誤判断の可能性が大いにあると言えます。
しかし、こと勝負の世界、争いごとの判断において、勝負師の貴乃花親方がそうそう誤解をするとは到底思われません。
これは、相撲協会と貴乃花親方の政治闘争です。つまり、勝負師として類まれな感性を持つ貴乃花親方が、ありもしない圧力を掛けられたと一方的に誤解して、早まって退職を決断したなどという見解は的外れです。
貴乃花親方は、この種の圧力はもはや通常の手段では回避できないと直観的に判断して引退を決意したのでしょう。結果として早まったのかもしませんが、この段階においての貴乃花親方の決断は、取り得る最善の判断であった可能性の方が高いのです。
相撲協会側には圧力の認識はなかったのか
そもそも相撲協会側が、自分達にマイナスになるようなことを言うはずはありません。たとえ圧力があったとしても、圧力はなかったというでしょう。しかし、文書や口頭での圧力をにおわせる具体的なものはなかったとしても、上述のとおり暗黙的な圧力はあったと考えます。
相撲協会側の方々も暗黙知の世界の人たちです。彼らも自然と戦いのやり方を身に着けています。反協会派である貴乃花親方から、最初に政治闘争は仕掛けられたのですから、相撲協会側は黙ってはおれません。
戦いにおいて、心理的な圧力を掛けるのは常套手段です。相撲協会側は、このことは十分に認識し、貴乃花親方の行動を心理的に縛っていったはずです。
つまり、無所属の親方をいずれかの一門に入れ、外堀を固め、所属先の未定が貴乃花親方一人なる状況を作為しました。その状況を好機とみなし、さらに貴乃花親方に心理的に圧力を掛けていくことを意図的に行った可能性があります。
相撲協会側には貴乃花親方を完全に排除する派と、貴乃花親方の勝手な行動を諌め、軍門に下らせる派が存在していると考えます。いずれにせよ、政治闘争が継続している限り、貴乃花は相撲協会の敵であるわけです。
ただし、相撲協会側の本当の敵が貴乃花親方であったのか、それとも相撲を愛してくれるファンであったのか、さらには将来を取り巻く相撲がどのような環境に遭遇するのかというという情勢判断については、相撲界という狭い暗黙知の世界で生きてきた方々には少し難問であるのかもしれません。
思い起こす「パールハーバー」
話しは少し飛びますが、今回の両者の対立には「パールハーバー」を思い起こします。太平洋戦争の口火となる真珠湾攻撃は、日本の開戦通告が攻撃開始後の40分後になったことから、アメリカは日本の“卑怯なだまし討ち”を喧伝しました。
しかし、ルーズベルトはすでに蒋介石軍を支援し、厳しい対日経済制裁を発動し、対日決戦を行う決意を固めていました。
実は、真珠湾攻撃以前にもアメリカはわが国を攻撃するという計画もありました。これは350機会のカーチス戦闘機、150機のロッキード・ハドソン爆撃機を使用し、木造住宅の多い日本民家を焼夷弾を使用して爆撃するというものです。
実際には、欧州戦線への爆撃機投入を優先したため、この計画が遅れて真珠本攻撃となったにすぎないのです。むしろ、卑怯なだまし討ちはアメリカが行っていたかもしれません。
日本は1931年の満州事変以降、欧米からの圧力を受けました。そして国連から脱退して孤立化します。アメリカから石油をはじめとする資源の供給を停止され、じりじりと追い込まれています。そして対米戦争を最終的に決定したのが「ハルノート」です。これが提出された翌日の11月26日、日本はアメリカとの交渉の打ち切りを決定しました。
日本にも非難される点は多々ありました。しかし、欧米による歴史的なアジア侵略、迫りくるロシアの脅威、資源の枯渇などから、やむなく大陸進出を選択し、 欧米列強からのアジアの開放を目指したのです。
そこには、自らの利益追求を目的にアジアに侵略した欧米よりも十分な正統性があったと考えます。
貴乃花親方は孤立化した日本であった
まさに今回の貴乃花親方は、当時の日本の状況であると思われます。
貴乃花親方の行動には批判される点が多々あります。 しかし、ガチンコ力士であった親方が八百長につながる馴れ合い所帯の体制の撤廃、暴力の追放などを柱とした、相撲改革を目指したことは間違っていたとはいえません。
ただし、急進改革を求めるあまり、他との協調性を欠き、孤立化し、相撲協会側との関係が深刻化しました。
貴乃花の今回の行動を、私はかつての日本の状況とだぶられせてしまい、無念な感情から抜け出せないのです。
姑息な印象を受ける相撲協会
一方の相撲協会側のやり方が間違っているとは、私は思っていません。いささか反協会派の貴乃花親方の包囲網の形成を焦った感はありますが、組織としてはむしろ当然の措置だったのでしょう。
しかしながら、外堀を固めながら、じりじりと貴乃花親方を追い込んでおきながら、最後にのところで貴乃花親方の想定外の行動を受けた。
そのため、「9月27日の時点で一門に所属していない親方がいたら話し合いをする予定だった」「一門は受け入れる予定であった」などとのマスコミ報道を使った弁明は、詭弁以外の何物でもありません。
さらには引退届けが正式でない、所属力士の移動届けにも瑕疵があるなどとの芝田山親方の発言です。 そして未だに退職届は受理していないので、9月27日の番付編成会議に出るべきであるとの見解を主張しています。
そして、同編成会議に出なかったことにマスコミは「無断欠席」と書き立てるのです。すでに貴乃花親方は明確に引退の意志を明確に表示し、その理由を相撲協会の圧力だと言っているのです。少なくとも、無断であるとはいえません。
なにゆえ、貴乃花親方一人だけが無所属で、全員の親方が一門に所属した状況の会議に参加できるというのでしょうか。それこそ、明確な圧力行為ではないでしょうか?
相撲協会のこうした言動は法律的にも適正とはいえません。また、これには、日本を戦略的に追い込んで起きながら、日本の卑怯なだまし討ちを喧伝して、開戦気運を盛り上げたアメリカのやり方と非常に似た、ずるさ、いやらしさを感じます。
つまり、相撲協会のやり方は、武士道精神の潔さがまったく感じられないのです。いささか姑息手段がすぎるように感じます。
双方に望むこと
今後の貴乃花親方も、敗戦した日本のように前途は多難なのでしょう。 でも、少年に相撲を教えて、相撲界を盛り上げたい、その言におおいに賛成です。
相撲協会はもはや枝葉末節にこだわらず、早々に貴乃花親方の引退を認めていただきたいと思います。そして、同親方の行動にも一理あることを認めて、是正できることに取り組んでいっていただきたいと思います。